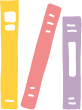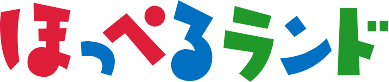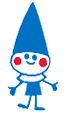ほっぺるだより
Letter
ほっぺるランド 新島橋かちどき
園で起こり得ることを想定した救急対応(園内研修)

~保育園という場所~
保育園は朝から夜まで、子どもの声が
響き渡る賑やかな場所です。
通う子どもにとっては第2の家であり、
保育者にとってその子たちは我が子と
言ってもいいのかもしれません。

子どもを「預かる」場所であると同時に、
子どもと「共に生きる」場所でもあります。
子どもは日々成長し、
その瞬間を生き、
だから常に快活で生命力溢れる
息吹が駆け回っています。
保育園は
子どもが成長する場所であると同時に、
保育者も成長する場所なのだと思います。

~その人だからできること~
保育者はそれぞれ自分らしい、
自分だからできる保育を行っています。
ピアノが上手な人は音の豊かさや
楽しさを子どもに伝え、
製作が得意な人は造形美や想像性を
子どもの心に種をまき、
運動が好きな人は、運動の資格を活用し
体操教室をやる。
保育者はそれぞれに与えられた
役割を担いながら、自分だからできることや
自分の好きなことを保育に活かします。

元気に生活する子どもとの時間の中で
大切なのは、看護師です。
子どもが健康に過ごすため、
体の安全・安心を専門的な知識で守る方たち。


~園内研修~
世の中には便利なものが沢山あります。
生活を快適にするものから、
欠かすことができないものまで。
中でも普段は必要ないけれども、
イザと言う時に必ず必要になる緊急性が高い
ものがあります。
それは、AEDです。
商業施設や駅、
人が沢山利用する場所には必ず
置いてあるもの。

AEDをはじめ、保育者は救急についての
研修を受けたりしいざという時に備えています。
子どもは体がまだ未発達で、
普通救命救急を土台とした
独特な対応が必要になります。
例えばAEDの使用時
大人はパッドを左右に貼り付けますが、
子ども背中と胸に貼り付けるなどです。
研修を受けその内容を確認するため、
救命救急の園内研修を行いました。

~具体化していく~
ただ使い方を説明するのではなく、
起こりうるケースを想定した演習的な内容。
午睡時に呼吸が止まった乳児を発見した際、
保育者はどんな役割分担で動いていくのか。
救急車を呼び、AEDを持ってくる人、
心肺蘇生をする人、
病院に搬送した時により的確に
状況や子どもの様子を伝えられるよう記録をとる人。

一連の流れを説明するために
看護師が見本で示してくれた後、
0歳クラスの先生が取り組みます。


具体的に、より具体的にしていく。
単に「やる」のではなく、
「なぜ必要なのか」
「どうしていけばいいのか」
「どうすればいいのか」
を細かく確認をしていきます。




救命は大事なこと。
大事なことだから、しっかりと取り組むのが当然。
でもそれだけではありませんでした。
看護師が持つ熱量が、保育者へと伝わる。
伝わる熱量が保育者をより突き動かす。



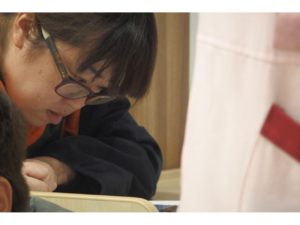

~繋がる先に~
主任であるのぞみ先生がつい先日、
プライベートの時間に具合を悪くされ
倒れてしまう人を見つけたそうです。
のぞみ先生は救命の講習を受けたからこそ、
動けたそうです。
これって、ともて凄いことだなと
話を聞いていて思いました。
知っていなければ、できない。
でも知っていれば、できる。
知っているから、その瞬間に動ける心が培われる。




ほっぺるだより
Letter